2025年5月、江藤拓農林水産大臣(以下、江藤大臣)の発言がSNS上で大きな波紋を呼び、炎上しています。
問題になったのは「私は米を買ったことがない」「玄米を選んでほしい」などの発言。
国民からは「自慢?」「感覚がズレている」といった批判が相次ぎました。
今回の記事では江藤大臣が無能とまで呼ばれている理由についてまとめました。
発言の真意や今後の去就についても考察します。
江藤農林水産大臣が無能と批判されたきっかけ
まず、江藤氏が発言した内容をみてみましょう。
「私はコメは買ったことはありません、正直。支援者の方々がたくさんコメを下さる。売るほどあります、私の家の食品庫には」
「わざとじゃないですけども、いろんなものが混じっている。黒いやつとか石とか入っている。いつも家庭内精米をした上で、コイン精米機に持って行く。ですから、精米できないときは、玄米で売るということも、今回は可能とするので、効果が期待できるんじゃないか」引用:NHK
発言は2025年5月18日、佐賀市で開かれた自民党県連の政治資金パーティーでの講演中のことでした。

炎上した理由を掘り下げてみてみましょう
理由①自慢していると捉えられたから
江藤大臣が炎上した理由1つ目。
現在、日本ではお米の価格高騰が止まりません。
気軽に買える商品ではなくなっています。
そんな中で「米を買ったことはない」さらには「売るほどある」という発言は、自慢や嫌味と捉えられてしまいました。



一昔前なら同じ発言でも自慢話に聞こえなかったかもしれませんが…。
今はお米は高級品になりつつありますもんね。
また、後ほど詳しく紹介しますが農林水産大臣の仕事の1つに「食糧(米も含む)の価格調整」もあります。
この役割を果たしていないのに、加えてお米の価格を問題視していないような発言が、国民の反感を買ってしまったと考えられます。
理由②いただき物への感謝がない
江藤大臣が炎上した理由2つ目。
問題となったのは支援者からもらったお米に対して
「いろんなものが混じっている。黒いやつとか石とか入っている」といった発言ですね。
政界でもこの件について言及している方がいたので見てみましょう。
こりゃ、ないわ。
— 蓮舫🗼れんほう🇯🇵 (@renho_sha) May 19, 2025
お米の値段の高さもわからないし、いただいたお米への敬意もない農林水産大臣。https://t.co/QcyWcxD9me
連邦氏も敬意がない点について呆れているコメントを投稿。
貰い物に対してありがたみを感じていないような発言が問題となってしまいました。



どんな形であれ、今の時代にお米を贈られるのは羨ましい限りです
理由③「ウケ狙いをした」と発言
江藤大臣が炎上した理由3つ目。
これは、翌日5月19日に講演中の発言を撤回した時に判明したことです。
「売るほどあると言ったのは言い過ぎだった。講演になると会場も盛り上がっていたので、うけを狙って強めに言ったが、売るほどということはない」
引用:Yahooニュース
このウケ狙いをしたという事実について、「不謹慎」という声があがりました。
謝罪をしたつもりでしたが、余計に逆撫でする結果となってしまいました。



たしかに冗談としては受け取れないかもしれません…
江藤農林水産大臣の辞任の可能性
現時点では辞任には至っていません。
「結果を出して責任を果たす」という姿勢を示しており、今後の動向に注目が集まっています。
しかし、世論がさらに悪化すれば、引責辞任という流れになる可能性もあります
農林水産大臣の仕事内容
農林水産大臣は、日本の農業・林業・漁業・食品政策のトップです。
農林水産省の代表として、国民の「食」や「農」に関する課題に取り組んでいます。
・食料の安定供給を守る(コメ・野菜・魚などの生産・価格調整)
・農家の支援や所得安定のための政策づくり
・輸出振興や輸入調整(和牛や水産物の輸出など)
・食の安全・品質管理(食品表示や産地偽装対策など)
・災害や不作時の備え(備蓄米の管理もここに含まれます)
農林水産大臣と米の関係
農水省の中でも特に重要なのがコメ政策です。
・日本の主食であり、国民の食生活の根幹
・農家の大部分がコメ作りに関わっている
・食料安全保障の観点から、政府が「備蓄米」を保有している
・天候や災害による価格変動が起きやすい
・輸入規制や関税の影響も受けやすい



米との関係が奥深いポストなんですね!
世間の声
感覚がズレている
もう少し国民の生活をわかってほしい
早く米の価格をどうにかして
ネガティブな意見が少し多い印象でした。



政界からも批判や代わりに謝罪するまでの事案になっています
まとめ
江藤大臣の発言は意図がどうであれ、伝え方次第で炎上してしまうという典型的な事例となりました。
情報発信の立場にある人ほど、相手の立場や感情に寄り添った言葉選びが求められます。
今後、江藤大臣がどのように信頼回復を図るのか引き続き注目ですね。
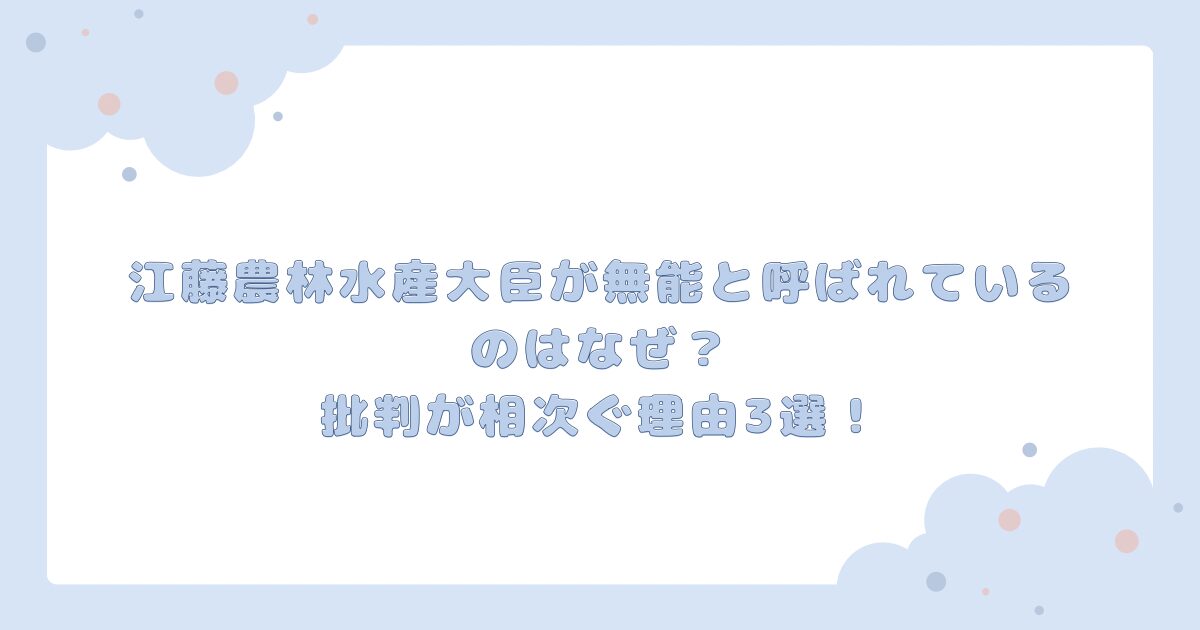
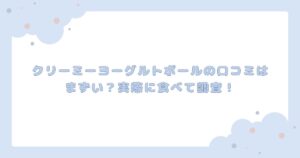
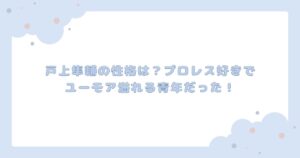
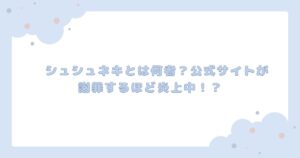
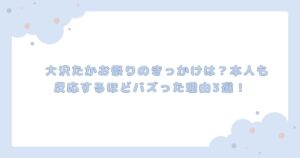
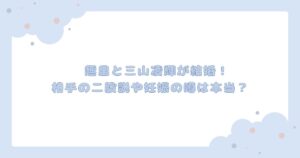
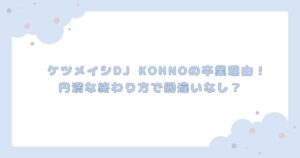
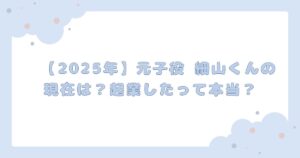
コメント